カニ
客車へサービス用電源を供給する発電機搭載車のこと。電源車。重量が47.5トン以上の「カ」と荷物車の「二」で「カニ」。

かぶり
複線などで対抗する列車や、線路沿いの道路を走るトラックが写り込んで車両と重なること。
かぶりつき
運転室の後ろから前面展望を見ること。
カマ
いわゆるボイラー=罐(かま)=機関車。蒸気機関車だけでなく電気機関車もカマって呼ばれたりする。

キ
鉄道車両の種別記号の一つで「気動車」を表す。キハとかキニとか。以前は除雪車や貨車にも「キ」が使用されていた。

キセ
クーラーやタンク貨車の外装保護板のこと。例

キセル
いわゆる不正乗車の手口のこと。乗車区間の途中運賃を支払わずに改札を通る方法でれっきとした犯罪。喫煙具のキセルが両端にしか金属が使われていないことに由来。
キマロキ編成
除雪のための特別編成列車のこと。ラッセル車(キ)・ロータリー車(ロ)・マクレー車(マ)。ラッセル車(キ)で構成されることから。

キャブ
機関車の運転室のこと。英語の「Cabine(キャビン)」に由来。
ク
貨車種別を表す記号。車を運搬する車運車。もしくは電車などで運転台を有する車両のこと。
グモる
インターネット掲示板で生まれたスラング。人身事故のこと。
グリーンマックス
鉄道模型メーカーの一つ。略称はGM。車両や建築物などのキットを販売していることで有名。
グリーン車
国鉄およびその後継のJRグループにおいて、一般車両よりも上級の座席を提供する車両を指す。特に新幹線や主要な在来線の列車に設定されることが多い。
グロベン
丸いグローブ型ベンチレーターのこと。換気効果は高い。

ケ
貨車の用途記号の一つ。重量計を校正するための検重車のこと。
ゲージ
軌間、または鉄道模型の線路幅のこと。日本では9mmのNゲージ、16.5mmのHOゲージが主流。なお、どのゲージが一番良いかは火薬に引火させることになりかねないのでタブー視される。

ゲタ電
通勤型電車のこと。普段使いで乗れる電車という意味を込めたもの。
ケツ
列車の最後尾のこと。
コルゲート
車体の側面にある筋状の加工のこと。波板。薄いステンレス板の強度を増すためのもの。各社で取り入れられているが、近年はその数を減らしつつある。

仮乗降場
定期的な運行が行われない駅や停留所。特定のイベントや需要に応じて一時的に運行される場合があります。
家禽車
家禽(鶏や鳥など)を輸送するための専用車両。通気性や温度調整などの配慮がされています。

家畜車
家畜(牛や豚など)を輸送するための専用車両。安全で快適な環境を提供し、動物の健康を保護します。

架空鉄道
空想上の鉄道を経営すること。経営から路線、ダイヤ作成まで行うガチ勢も多数。
架空電車線方式
電車が走行中に供給する電力を、架空の電線から受ける方式。走行中でも絶えず電力を供給できるため、長距離走行に適しています。

架線
電車や電気機関車に電力を供給するために、軌道上に張られた導線。列車が通過する際に接触し、電力を受け取ります。

架線
電車や電気機関車に電気を供給するための電線のこと。

火災車両
炎上したもの……ではなく、鉄道模型で加工や整形不良で大きく歪んだものを指す蔑称。
火室
蒸気機関車において石炭などの燃料が燃える場所のこと。ここの熱で蒸気を発生させる。
火夫
蒸気機関車の運転士の助手。燃料を投入し、ボイラー内の蒸気を生成する作業を行います。

荷物車
貨物列車で荷物や小包を輸送するための車両。旅客の荷物や郵便物の運搬に使用されます。

荷物列車
荷物や貨物を専門に運搬する列車。旅客列車とは別に、貨物の運送を行います。

貨客混載
旅客列車に貨物を併せて運搬すること。地域交通や短距離列車で行われ、利便性と効率を高めます。

貨車
貨物を輸送するための鉄道車両。種類に応じて荷台の形状や仕組みが異なります。
貨車移動機
貨車を手動や機械で移動させるための装置。貨物駅などで貨車の位置調整に使用されます。一般にはエンジンやモーターで動く小型機関車や廃車となった旧型電車、アントと呼ばれる専用の小型機が使用されます。

貨車車票
一部の路線や列車で、貨車の荷台で乗車するための切符。特定の利用者に提供されます。

貨物駅
貨物の集荷・仕分け・配送を行うための駅。貨物列車の運行や荷役作業が行われます。
貨物時刻表
貨物列車の運行時刻を示す表。貨物の出荷や到着のスケジュールを確認するのに用います。
貨物線
貨物専用の鉄道路線。貨物列車の運行や輸送に特化した軌道です。
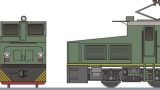
貨物列車
貨物を運搬するための列車。異なる種類の貨車を組み合わせて運行され、物流を支えます。

解結
貨物列車などで連結されている車両を切り離すこと。貨物の仕分けや配送を行う際に行われます。
回数乗車券
特定の区間や路線で複数回乗車できる切符。定期的な通勤や利用に適した券種です。
回生ブレーキ
電車や電気機関車が減速や停止時に、発生した電力を回生し電力供給に再利用するブレーキ方式。

回送
空車や運用準備などの目的で、車両を運転すること。乗客や貨物を運ばない移動です。
回送線
車両の回送を行うための専用の軌道やルート。運用の要らない車両の移動に使用されます。
回送列車
空車や保守作業のために運行される列車。運転士や車掌は乗務せず、車両の移動を行います。
回転式クロスシート
座席が180度回転できるクロスシート。座席の向きを変えることで、列車の進行方向に座ることができます。

快速急行
主要駅間を結ぶ高速で停車駅の少ない列車。一般の急行よりも速い運行を行います。

快速特急
特定の主要駅間を結ぶ、最速かつ高速な列車。長距離の移動を迅速に行うために運行されます。
快速列車
主要駅と中間駅を結ぶ、一般的な急行よりも速い運行を行う列車。早く目的地に到着するための選択肢です。

改軌
軌道の幅を変更する作業。軌道幅が異なる路線間での連結や運行を可能にします。

改札
駅の入口や出口で、乗車券の検札や整理を行う場所。正規の切符を持たない者の乗車を防ぎます。
界磁チョッパ制御
電気機関車や電車の制御方式。電動機の界磁(励磁)を制御し、効率的な加速や減速を実現します。

界磁位相制御
電気機関車の制御方式。電動機の界磁位相を変更し、効率的な動力伝達を行います。

界磁添加励磁制御
電気機関車の制御方式。界磁に直流電流を加えて電動機の性能を向上させる制御方法です。

開かずの踏切
道路と鉄道が交差する場所で、車両が通過する際に踏切が開かずに通過する形態。安全性の向上を図ります。
各自工夫
鉄道模型分野でユーザー側で工夫して作ること。キットによっては「細部表現は各自工夫のこと」と指示されていことも。
額縁スタイル
前面部が一段凹んだ形状の鉄道車両のこと。南海9000系など。

滑走
空転のこと。一般にはブレーキ時の滑りを指す。列車が止まらないだけでなく、車輪やレールが偏摩耗するので避けるべきとされる。
汽車
蒸気機関車のこと。鉄道ファン以外では電車など含めて全て「汽車」と呼んだりする。

軌間
軌道の2本のレール間の距離。異なる路線や国によって異なる軌間があります。
軌道
列車が走行するためのレールや枕木、線路などの設備。安定した運行を支えます。
軌道
鉄道が通る線路、ガイドレールなどの総称。「線路」の同義語。また一般的な鉄道を「鉄道」、路面電車を「軌道」と呼び分けたりもする。

軌道修繕
軌道の傷みや欠陥を修復する作業。定期的な保守が行われます。
軌道線路
列車が走行するための軌道。直線や曲線、勾配などが含まれます。
軌道保守
軌道や枕木、線路などの保守作業。安全性と快適な走行を維持します。
急行形車両
主に急行列車に使用される、高速・快適な設計の車両。長距離移動に適しており、旅客の利便性を向上させます。

急行券
急行列車に乗車するための切符。一般の普通列車よりも速く移動できるため、高速交通を利用する際に購入されます。

急行線
主要都市間を結ぶ高速で停車駅の少ない列車用の専用線。急行列車のスムーズな運行を支えます。

急行列車
主要都市やエリアを結ぶ、停車駅の少ない高速列車。長距離の移動に利用されることが多く、効率的な移動を実現します。

救援車
障害や事故などで故障した列車や車両の救援や修理作業を行うための特殊な車両。

旧型客車
鉄道車両の中で、年数が経過したり設計が古いもの。一般には国鉄の10系客車以前のものを差すことが多い。旧形客車、旧客とも表記する。

旧型客車
戦前・戦中くらいまでの客車の総称。年代の区切りは様々。とはいえ令和、客車が淘汰された時代では対義語としての「現用客車」も死語になっている気も。

旧形国電
戦前・戦中くらいまでの電車の総称。大正ロマンあふれるオシャレなものから戦時中の資材不足の中で工夫を凝らしたものまで様々。

共通運賃制度
複数の鉄道事業者間で、一つの運賃体系を共有する制度。利用者にとって便益があり、スムーズな乗り継ぎが可能です。
共通乗車制度
複数の交通機関や路線間で、同じ切符やカードを使って乗り継ぐことができる制度。利便性を高めます。
橋上駅
鉄道駅が高架構造の上に設けられている形態。道路や他の鉄道との交差を解消し、スペース効率を改善します。
狭軌
軌間(軌道の幅)が広軌よりも狭い鉄道路線。限られたスペースで建設が可能であり、一部地域に適しています。

近畿車輛
鉄道車両メーカー。近鉄グループの一つ。鉄道車両などの生産を手掛ける大手。

近郊形車両
主に都市近郊の運行に適した、通勤や通学に利用される車両。高頻度運行や短距離移動に向いています。

区間
鉄道路線が分割された部分。駅間や地域ごとに区分され、運賃計算や運行管理に用いられます。
区間快速
特定の区間間を結ぶ高速列車。停車駅を限定しているため、迅速な移動が可能です。

区間車
特定の区間間を結ぶ普通列車。多くの駅で停車し、地域内の移動に適しています。
空気ばね
車両の車体や座席を支持するために使用される、圧縮空気を利用するばね。快適な乗り心地を提供します。

空気ブレーキ
圧縮空気を用いて列車のブレーキを制御する装置。安全な停止や減速を実現します。

空港アクセス鉄道
空港と都市を結ぶために設置された鉄道。旅客が便利に空港へアクセスできるようにします。

空港駅
空港内に設けられた鉄道の駅。旅客が空港から鉄道を利用する際の出発・到着点となります。

空港連絡鉄道
都市と空港を結ぶために設置された鉄道。旅客がスムーズに空港へ移動できるようにする交通インフラ。

空車
輸送の際に荷物が入っていない空の車両。貨物や乗客を輸送する際に利用されます。
空転
加速時に車輪がスリップすること。路面状態や乗客数により起こりやすく、いかに空転させないかは運転手の手腕にかかっている。雪の日は顕著。
屑鉄
不要となった金属スクラップのこと。その意味を込めて迷惑行為を行う鉄道ファンのことを指したりもする。
軍用列車
軍事活動や兵站のために軍が運用する列車。物資や兵員の移動に利用されます。

形式写真
資料用に撮影されたアングルの写真のこと。1両ごとに側面、前面それぞれから撮影されていることが多い。鉄道模型ファンにとって最も欲する写真。
経路特定区間
切符の発売や運賃計算を行う際、特定の区間を指定した区間。運賃設定や運行管理に使用されます。
警笛
鉄道車両が発車や接近を知らせるために鳴らす音の信号装置。安全確保のために重要な役割を果たします。
軽便鉄道
主に観光や地域交通目的で運行される、狭軌の軽量な鉄道。景色を楽しみながら移動できることが特徴です。
穴
時刻表の列車間隔のこと。一般乗客にとっては待ちぼうけ。乗り鉄で言えば駅を探索する時間、撮り鉄でいえば機材準備と休憩にあたる貴重な時間。
建築限界測定車
軌道の周囲の建築物や構造物の位置や高さを測定するための専用車両。路線改修や新設時に使用されます。
懸垂式モノレール
車両が軌道から吊り下げられた形式のモノレール。都市部や観光地などで特徴的な交通手段として用いられます。

検重車
軌道の状態や車両の重量を測定するための専用車両。保守や点検作業のために使用されます。
固定式クロスシート
座席が向かい合う形式で、車内の中央に通路があるクロスシート。車内の利用スペースを最大限に活用します。

跨座式モノレール
車両が軌道の上にまたがる形式のモノレール。軌道が幅広く視界が良好なため、景色を楽しみながら移動できます。

御料車
皇族が乗るためのお召し列車のこと。かつては特別で豪華な内装が施された客車が用意されていた。

交換駅
複数の路線が交差し、乗客が乗り換えるための駅。便利な乗り継ぎを提供します。
交直流電車
交流と直流の両方の電力を利用して走行する電車。異なる電化方式の路線を連結する際に使用されます。

交流型電車
車両の駆動や制動に交流電力を使用する電車。交流電化された路線で運行されます。

交流電化
鉄道路線に交流電力供給設備を設置し、電車が交流電力を使用して運行する電化方式。
公営鉄道
国や地方自治体が運営する鉄道。公共交通の一環として運行され、地域の移動や生活を支えます。
工作車
線路や設備の保守や修繕を行うための専用車両。線路の点検や保全作業に使用されます。
広軌
軌間(軌道の幅)が広い鉄道路線。速度や安定性が向上するために新幹線などの路線で適応されます。
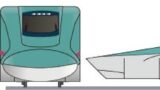
控車
指定の駅において、特定の列車に接続するために待機する車両。待ち時間を利用して乗り換えを行います。
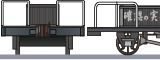
甲種輸送
甲種鉄道車両輸送(こうしゅてつどうしゃりょうゆそう)とは、日本貨物鉄道(JR貨物)などの貨物鉄道事業者が行う一種の輸送方法です。この方法では、輸送する鉄道車両(仮設を含む)を専用の機関車で引っ張って、貨物列車として輸送します。一般的には「甲種輸送(こうしゅゆそう)」と略して呼ばれることもあります。
甲種輸送
鉄道車両を線路上を走行させて輸送すること。自力では走らないので機関車で牽引される。新車両が登場すると甲種輸送されるかと待ち構える鉄道ファンは多数。
行先標
列車の行先や運行情報を示す表示板。駅やプラットホームで乗客に情報提供を行います。
鋼索鉄道
車両が鋼索(ケーブル)に引かれる方式の鉄道。急勾配や山岳地帯での運行に適しています。

高架駅
駅が高架構造の上に建設された形態。地上の交通や建築物との干渉を避け、スペースを有効活用します。
高架化
鉄道路線を高架構造に転換すること。地上での交通障害を解消し、車両や乗客の移動をスムーズにします。

高架鉄道
軌道が高架構造の上に設置された鉄道。都市部の交通混雑緩和や高速移動を実現します。

高速
速い速度での運行を指す用語。高速列車や高速道路などで利用されます。
高速化
鉄道路線や列車の速度を向上させる作業や改良。スピーディな移動を実現するための取り組みです。
高速貨物列車
高速で貨物を運搬するための列車。効率的な物流を支えます。

高速鉄道
高速で走行する鉄道。専用の高速路線や技術を使用し、長距離移動を効率的に行います。
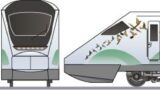
剛体架線
電車などが走行する際に接触する導電性の架線。車両との間で電力供給が行われます。
国際列車
異なる国を結ぶ列車。国境を越えて運行され、国際的な旅行や輸送に利用されます。

国鉄
国有鉄道の略称。国が所有し運営する鉄道を指します。

国鉄形
国鉄時代の電車や気動車をまとめて差す言葉。令和の今でも少数ですが残っています。

国鉄色
国有鉄道が運行していた列車の車体塗装やデザイン。各地域で特徴的なカラーリングが存在しました。

国鉄色
国鉄が制定したカラーリングのこと。電車や気動車などそれぞれに定められていた。近年はリバイバルカラーとして再登場し、脚光を集めることも。

込め不足
列車の車両に乗客が詰め込まれていない状態。利用者数が少ないことを意味します。
混合列車
旅客車両と貨物車両が一つの列車に組み込まれた形態。一部地域での運行に使用されました。
混雑率
列車や車両内の座席やスペースの利用状況を示す指標。乗客の密度や混雑度を示します。
切符
切符は、鉄道や公共交通機関の利用料金を支払うために発行される乗車証明書です。特定の区間や特定の列車などを利用する際に提示することで、利用者は適切な運賃を支払い、乗車することができます。切符は乗車駅や券売機、窓口で購入することができ、種類や利用条件によって異なるものが存在します。
片パン
片方のパンタグラフだけを上昇した状態。基本的に交流区間では片パンとなる。

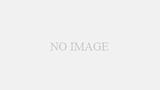
コメント