2階建車両
2階建車両は、列車の車両のうち、通常の1階部分に加えて2階にも座席やスペースを設けた車両を指します。これにより、より多くの乗客を収容することが可能となり、鉄道の輸送力を向上させる役割を果たします。

762mm
狭い軌間を持つ鉄道。狭い地域や山岳地帯などで運行され、特定の用途に適した鉄道路線を指します。一般には762mmやそれ以下の軌間を差すことが多い、

AGT(自動案内軌条式旅客輸送システム)
軌道に設置された案内軌条に沿って進むシステム。空港の連絡路線などで利用される自動運転の交通手段です。

ATC(自動列車制御装置)
列車の速度や位置を自動的に制御する装置。安全な列車間隔を保ちつつ効率的な運行を行います。

ATO(自動列車運転装置)
列車の運転を自動で行う装置。プログラムに従って運行し、安全かつ効率的な運行を実現します。

ATS(自動列車停止装置)
列車が信号や制御の指示に従って自動的に停止する装置。安全確保や信号無視の防止に役立ちます。

AT饋電方式
AT饋電方式( AT-feeding system, Auto-transformer feeding system)は、電気で駆動する鉄道車両が単巻変圧器を介し、電圧を半分にして給電する交流電化方式です。変電所の数を減らすことが出来る特徴があり、特に長大な路線で大電力を扱う場合に威力を発揮します。が、電圧を半分にするということは元の電圧が2倍となること。絶縁が困難かつ更新費が高価になるというデメリットもあります。
AWS(自動列車警報装置)
列車同士の安全な間隔を確保するため、自動的に警報を発する装置。列車同士の衝突を防ぎます。
A寝台
A寝台は、鉄道の寝台車両の中で、高い快適性を提供する最上級の寝台を指します。いわゆる一等寝台。個室やシャワー、トイレなどの設備が充実しているものもあり、長距離の夜行列車などで利用されます。

BT饋電方式
BT饋電方式は、鉄道の電力供給方式の一つ。交流電化で給電を行う方式で、通信回線への誘導障害が抑制できる利点があります。日本では東海道新幹線(開業時)や国鉄の交流電化区間で広く採用されました。現在はAT饋電方式へ更新が進んでいます。
B寝台
B寝台は、鉄道の寝台車両の中で、A寝台よりもリーズナブルな価格設定で提供される寝台を指します。個室や設備はA寝台に比べ簡素ですが、安価な宿泊オプションとして利用されます。

DXグリーン
DXグリーンは、鉄道の列車車両の中で、高級な内装や快適な座席を備えたクラスを指します。一般的なグリーン車よりも高級なサービスや設備が提供され、特に長距離の旅行に適しています。
HSST
HSST(High Speed Surface Transport)は、磁気浮上式鉄道の一種で、浮上する車体が軌道の上面に接触する方式を指します。磁気浮上技術を用いて高速での運行が可能であり、交通機関としての高速性と効率性を提供します。
ICカード
ICカードは、非接触型のスマートカード技術を用いた乗車券や支払いの手段を指します。公共交通機関の乗車やショッピング、決済など様々な場面で利用され、利便性とスムーズな取引を実現します。現在はSUICA、ICOCAなど様々な交通系キャッシュレスサービスが存在しています。
ICカードシステム
ICカードシステムは、ICカードを利用した決済や乗車管理を行う仕組みを指します。鉄道の乗車券購入や改札処理が効率的に行えるほか、異なる交通機関やサービスの連携にも活用されます。
ISOコンテナ
ISO規格に則り設計、製造されたコンテナのこと。国際規格のため国内外を問わず安全な輸送が可能。箱型だけでなく液体やガス輸送のためのタンクコンテナもあり。

Mobility as a Service
MaaS(Mobility as a Service)は、地域の住民や旅行者の個々の移動ニーズに合わせて、複数の公共交通機関やその他の移動手段を最適に組み合わせて検索・予約・支払いなどを一括で行うサービスです。観光や医療などの目的地への移動だけでなく、他のサービスと連携することで、移動の利便性を向上させたり地域の課題を解決する手段として重要です。
MT比
MT比(エムティーひ)とは、動力分散方式の鉄道車両において動力車と付随車の構成比率を示すもの。車両の重量、電動機の数、歯数比が同じ場合、MT比が高いほど加速性能が高くなります。一方で消費電力が増加し、経済性が悪くなってしまいます。路線の特性や運行ダイヤに応じたMT比で編成されることが一般的です。
OSR(過速度検知装置)
列車が速度制限を超えた際に自動的に警報を発する装置。安全な運行を確保します。
VVVF制御(可変電圧可変周波数制御)
電気機関車や電車の駆動方式。電圧と周波数を変化させることで、効率的な動力伝達を実現し、運行条件に合わせた制御が可能です。



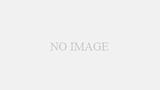
コメント